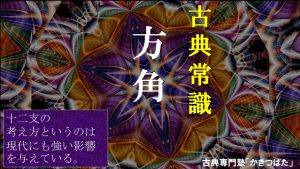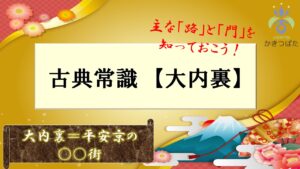古典常識「時刻」
今日は十二支の時刻です。
時刻についてお話をしていきます。
方角の所でもお話をしました通り、十二支というのは年、
例えば今年は卯年であるとか戌年であるとか、こういった年を表す事も出来ますし、
子の方角と言ったら北、卯の方角と言ったら東といったように方角を表す事も出来ます。
十二支の時刻
ここでは時刻を表す事が出来るのだ、というお話をいたします。

子の刻を0時とすると、ぐるっと子丑寅卯と回していくんですが、
24時間で一周しますので、午の刻は12時、お昼の12時という事になります。
ですから、12時の真ん中という事で、正午の刻と言うんですが、
現代でも正午というのはお昼の12時の事を指しますし、
午の刻より前の時間の事を午前、午の刻よりあとの時刻の事を午前と言います。
当然2時間なんですが、子の刻というのはこの0時を中心として
現代で言う前日の23時から翌日の1時までの2時間です。
丑の刻というのは1時から2時を中心にして3時までです。
寅は3時から4時を中心として5時までです。
5時から6、7時までが卯の刻というふうに、一つの時が2時間を表わしますが、
基本的な考え方としては0時を中心とした前後2時間という事になります。
ですので、例えば未と言われた時には
14時と答えたり、あるいは13時から15時までと答えてくれれば良いという事になります。
多くの場合大学入試で未の刻は何時ですか?と聞かれた時には
14時と答えられるようにしてくれれば結構です。
さて、今度はこれをさらに細かく分けていく考え方をしていきましょう。
いくら現代人と違ってざっくりとした時間感覚で生きていた?
この辺は現代文でもよく出題されます。
時計の発明とともに近代が出来るのだ、というような事を現代文で取り扱ったりしますが、
確かに近代的な時計なるものが出来る以前、
人々の時間感覚というのは割合にゆったりと流れていたようではあります。
とはいえ、いくらなんでも人と待ち合わせをする時に、未の刻に渋谷ね、と言われて
前後2時間ずっと待ってなきゃいけないというのもやはり不便です。
古文の世界では、この一つの時に対してさらに細かく四つに分ける分け方があります。
それが一つ二つ三つ四つという分け方です。
皆さんご存知の草木も眠る丑三つ時というのは、
午前2時から2時半まで、この30分間の事を指す訳です。
皆さんの枕元に幽霊が現れた時に、
3時とか4時だったらお前遅刻だ、と追い返してくれれば良いという事になります(笑)